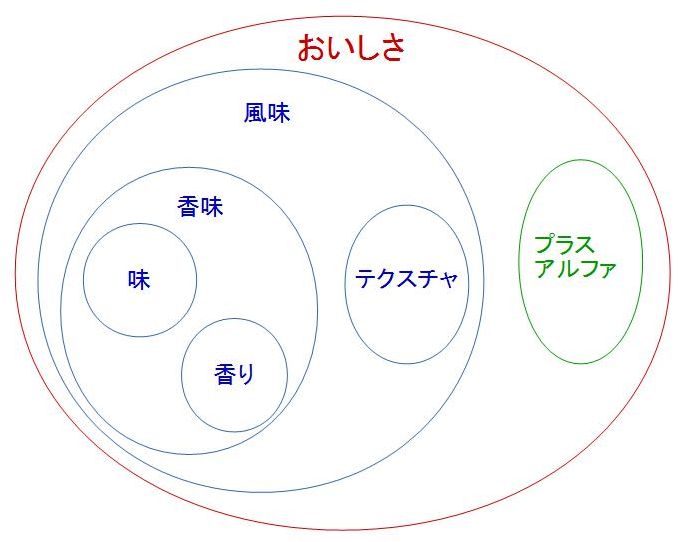昨日から焙煎&提供開始したプレミアムショコラ。
まだ2日目ですが、名前のせいもあって (^_^;) か順調な滑り出しです。
ありがとうございます (^^)
ところで、このプレミアムショコラですが、昨年と比べて豆の大きさが少し小さくなっています。
そこで、今回は「豆のサイズが小さくなること」についてです。
【豆のサイズが小さくなった?】
仕入先からの情報をそのまま書くと、以下のとおりです。
「通常はスクリーンサイズS17/18が90%以上なのが、15/16クロップはS17/18に加えてS16を40%配合している」
S1は1/64インチで、ミリメートルに換算すると、S18は7.14mm, S17は6.75mm S16は6.35mm です。
S18とS16で11%程度の差があり、体積だと3乗なので、30%近くの差があることになります。
以上は生豆の話ですので、加熱されて膨らんだ焙煎豆では、さらに差が目立つかもしれません。
今回このように小ぶりの豆が増える事になった理由は、産地であるブラジルの干ばつの影響だそうです。
コーヒーの果実が成長する時期に干ばつが重なったため、果実もその中の種子(コーヒー豆)も小ぶりになったとのことです。
まだ入荷していないダテーラサンライズのニュークロップも、同じような状態と聞いています。

【豆が小さくなることの影響】
一昔前までは「コーヒー豆は大きい方が良い」と言われていました。そういう話を聞いたことがあるかたでしたら「今年のは小さい」と聞くとネガティブに受け取られるかもしれません。
自分なんかは逆に、トマトやミカンなど小さいほうが濃厚で美味しくて、大きいと大味なイメージがあるのですが (^_^;)
今も各生産国の輸出規格では大きいほうが上級とされているケースが多いです。
例えばコロンビアの規格でスプレモ(S17以上)はエクセルソ(S14~16)より上級であり、取引価格も少し高くなります。
でも実際のところは、「大きい」と「美味しい」は、あまり関係ないように思います。
特に農園,地域,品種などが特定されているようなコーヒー豆の場合は、大きさによる先入観は捨ててしまったほうがいと思います。
強いて影響を挙げると、体積(スプーン)で豆を計量している場合に、粒が小さいことによって、かさ密度が増して、いつもよりコーヒー豆を多く使ってしまう可能性があるぐらいでしょうか。微々たるもんだとは思いますが。
【今年の風味を楽しみましょう】
農作物なので、その年の天候などの影響を受けるのは避けられないことです。
「今年のプレミアムショコラ」「今年のサンライズ」を楽しんでいただければと思います (^^)